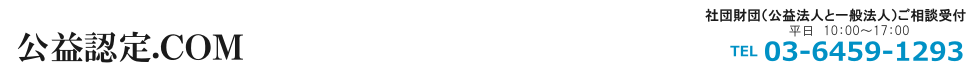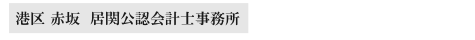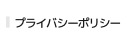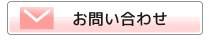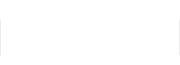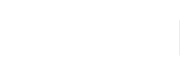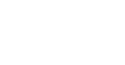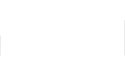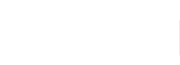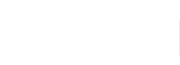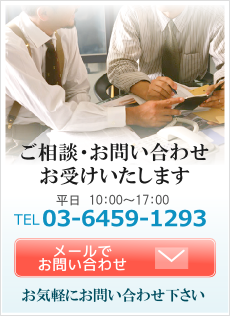内閣府メルマガ【R5.4.28臨時号】
HOME > 社団財団(公益法人と一般法人)に関する専門情報
内閣府メルマガ【R5.4.28臨時号】
内閣府メルマガ【R5.4.28臨時号】を転載します。
--------------------------
【目次】
1. 政府からのお知らせ
■新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議「最終報告(案)」に関する意見募集について
■第9回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議について
■第10回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議について
---------------------------------------
1.政府からのお知らせ
---------------------------------------
■新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議「最終報告(案)」に関する意見募集について
(省略)
■第9回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議について
令和5年4月17日、「第9回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」を開催しました。
第9回では、「中間報告」に関するアンケート調査結果のヒアリング及び最終報告に向けた主要論点について議論を行いました。
会議の概要は以下のとおりです。
(1)「中間報告」に関するアンケート調査結果のヒアリング
(公財)公益法人協会から、資料1に沿って、同法人が実施したアンケート調査の結果、本会議の中間報告は、概ね好意的に受け止められている旨の説明がありました。
(2)最終報告に向けた主要論点について
事務局から、資料3の主要論点ごとの制度改正の具体的な方向性及び資料4の最終報告骨子(素案)について説明を行いました。委員からの主な意見は以下のとおりです。
<収支相償原則の見直し>
・「中期的に均衡」の定義が運用で変わると混乱するため、法令上具体的に書くべき。
・収支相償原則について、現行法の根拠規定である公益認定法第14条を改正するならば、府令、ガイドライン等においても収支相償原則に係る規定を置くべき。
・遊休財産規制の見直しも含め、今回の見直し案では自由度が高まるものと思う。
・収支相償は、(公財)公益法人協会のアンケートでも完全撤廃への意見が二分されていることに留意して、不断の見直しを検討すべき。
<公益認定・変更手続の柔軟化・迅速化>
・届出事項とする範囲について、法人が判断できるようにプリンシプルベースで基準を明確にすることに加え、事例を整理して提供していただきたい。
・わかりやすい財務情報の開示も含め、できる限り前倒しでの対応に努めるとともに、法人がどのような対応が必要になるのか法施行前からの情報提供も検討いただきたい。
<合併手続等の柔軟化・迅速化>
・プリンシプルベースでの基準の明確化だけではなく、様々な事例・パターンを整理したものを提供してもらいたい。
<わかりやすい財務情報の開示>
・中小の法人に大きな負担とならないようにしていただきたい。
<法人機関ガバナンスの充実>
・会計監査人の設置義務を、現行の収益1,000億円以上から収益100億円以上としても対象となる法人は限られている。非営利法人は、株主によるチェックがないことから、学校法人や社会福祉法人等、他の法人類型の基準も踏まえて再度検討すべきではないか。
・会計監査人の設置義務の範囲について、公益法人は収益を目的とした法人ではないこと、学校法人や社会福祉法人は事業がある程度類型化されており、収入も補助金が多いことには留意すべき。
<公益法人による出資等の資金供給>
・長期の検討課題として、現行の他の団体の意思決定に関与することができる株式等の保有制限について、海外の制度も参考に見直してもよいのではないか。
・今の時代、営利団体も公益活動を行うことや経営支援となることも含めて検討していく必要があるのではないか。
<その他(スケジュール含む)>
・次期システムの運用開始が令和11年度からでは遅い。できるものから前倒しすべき。
・新制度が施行された際に、内閣府、都道府県の職員が新制度に即して対応いただけるように、研修や周知をしっかりと行っていただきたい。
・インパクト測定・マネジメントの意義はこれまでの会議でも確認してきたところであり、最終報告に、今後の普及の仕方等を盛り込んでいただきたい。
・全体として、中間報告を踏まえて具体化がなされており、非常に良い方向性。
■第10回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議について
令和5年4月27日、「第10回新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」を開催しました。
第10回では、最終報告(案)ついて議論を行いました。
会議の概要は以下のとおりです。
事務局から、資料1及び資料2に沿って、最終報告(案)について説明を行いました。委員からの主な意見は以下のとおりです。
・最終報告(案)について、全体としての方向性に賛同する。
・今回の改革について、法人の自由度の拡大の観点から検討が行われるとともに、自律的ガバナンスや事後チェックの重点化などについても検討いただいたことに感謝。
・今後、制度の詳細な検討が進められると思うが、民間による公益活動の活性化という今回のコンセプトを十分に踏まえていただきたい。
・最終報告(案)において、「国民の意見を幅広く聴取しつつ検討」や「不断の見直し」とあるが、これは切にお願いしたい。
・今回の見直しにより、収支相償原則が中期的な収支均衡に生まれ変わることで、現場でのしこりはだいぶ軽減するものと思う。
・公益充実資金や遊休財産に関する情報開示については、法人運営の透明性の向上による国民からの信頼確保という趣旨から、国民にとってわかりやすいものとすることが大事。
・定期提出書類における別表作成の見直しは法人負担の軽減になると思うが、新たに求められる区分経理(内訳表の作成)について、特に小規模法人への影響がどの程度あるかが懸念。
・役員の利益相反取引の情報開示については、法人が困らないよう丁寧な説明が必要。
・評議員の選任について、選考委員会の設置等が推奨とされているが、実質的な義務とならないようにしていただきたい。
・外部理事の導入に当たっての小規模法人の定義をどうするかは疑問が残る。
・外部理事について、会社法での規定を踏まえ、公益法人に多額の寄附を行っている団体等の関係者については、外部理事に当たらないとすることもご検討いただきたい。
・公益法人では、資金の拠出を受けている団体の関係者を外部理事としている実態もあるため、外部理事についてはその点も踏まえてご検討いただきたい。
・インパクト測定・マネジメントについて、事例集を作成して終わりではなく、官民が連携して普及を進めていくことが重要。
・公益法人による出資については、特定の公益に資することを主目的としていることが原則になると思うが、収益が出ることをもって絞るものではないという海外の事例も踏まえてご検討いただきたい。
・出資について、近年で状況は大きく変わってきている。変化、多様性を取り入れつつ、自由度を拡大することが新しい資本主義の実現にもつながるものと思う。出資に公益信託を活用することも検討してよいのではないか。
・公益活動における相互のシナジーを図る観点から、公益法人が認定取消しを受けた場合に、公益財産の残額について公益信託を設置したり、公益信託に贈与したりする方向性等もご検討いただきたい。
・公益信託については、投資等の新しい動きとともに、その特性を踏まえて、まずはより使われる制度にすることが大切である。
=====================================================
以上 公認会計士・税理士 居関 剛一