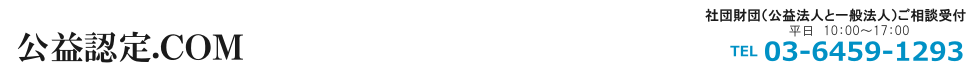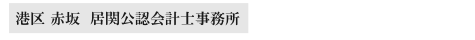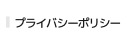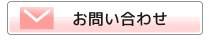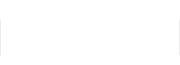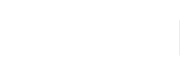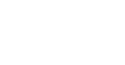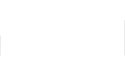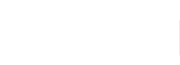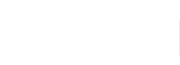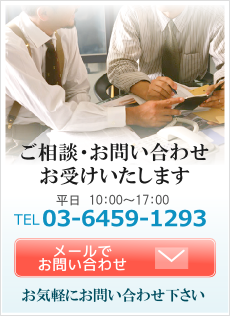指定寄付の事業が廃止され寄附者の意向確認ができない場合【内閣府メルマガR5.3.6】
HOME > 社団財団(公益法人と一般法人)に関する専門情報
指定寄付の事業が廃止され寄附者の意向確認ができない場合【内閣府メルマガR5.3.6】
「内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和5年3月6日発行」
に面白い論点の説明がありましたので、以下に転載します。
------------------------
1.前提
使途が指定された寄附金の対象事業について、長年実施してきたが時代のニーズに合わなくなり法人が経営判断として廃止したり、その他法人の責めによらない事情で廃止したりした場合において、寄附者の死亡、関係者(相続人等)の存在が確認できない等の理由により、手段を尽くしても当該寄附金の新たな使途指定の意向が確認できない場合、当該寄附金が「死蔵」されてしまう恐れがあります。
このような場合、当初指定された使途以外の使途に寄附金を使うことについて法律面と会計面で考え方を整理しましたのでご紹介します。寄附金の受取り方は法人により様々ですので、寄附金を受け取った時の状況を再確認していただき、寄附金の取り扱いの参考にしていただければと存じます。
2.法律上の考え方(整理)
上記1.前提のような場合について、学説では諸説ありますが、例えば、
(1)使途が指定された寄附金を「使途として指定された公益目的事業Aが存在するにもかかわらず、A以外に使用すること」を解除条件とする解除条件付贈与(民法第127条)として受け取ったと考え、Aの廃止により、解除条件が事後的に不能になり、結果として条件が消滅した(民法第133条第2項)、
(2)当該寄附金を「Aに使用すること」という負担が付いた負担付贈与(民法第553条)として受け取ったと考え、Aの廃止により、Aに使用することが不可能になった、
(3)使途が指定されたとされる寄附金であっても、実質的には使途の希望の表明に過ぎない、
と捉えることにより、使途の指定がないものと考え、Aに近い他の使途に用いることは排除しないと解することも可能ではないかと考えられます。
なお、今後、使途が指定された寄附金を新たに受け取る際、当初の使途に使用できなくなった場合の取扱いも事前に当事者間で明確にしておくとよいでしょう。
3.会計処理について
会計上は、寄附者からの「使途の指定」のある寄附金が、当該使途に沿って使用された等の場合に「使途の指定の解除」がなされ、正味財産増減計算書(内訳表)において、指定正味財産増減の部から一般正味財産増減の部への振替が行われることが一般的な会計処理(考え方)です。
しかし、上記1.のような場合、当該寄附金について、寄附者の合理的意思として上記2.のように構成できるときには、機関決定の上、「使途の指定の解除」として、正味財産増減計算書(内訳表)において、指定正味財産増減の部から一般正味財産増減の部へ振替え、当該寄附金相当額を他の公益目的事業の特定費用準備資金に積立てる等も可能と考えられます。
なお、本記載はあくまでも考え方の一例であり、法人において諸々の事情を考慮し適切に判断していただくことが必要です。
【参照条文】
民法(明治二十九年法律第八十九号)
(条件が成就した場合の効果)
第127条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
(不能条件)
第133条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
(負担付贈与)
第553条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
----------------------------
内容的には、ごくごく当たり前の結論なのですが、法的にきっちり説明がされています。
以上 公認会計士・税理士 居関 剛一